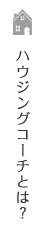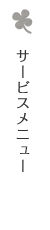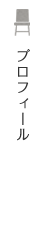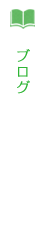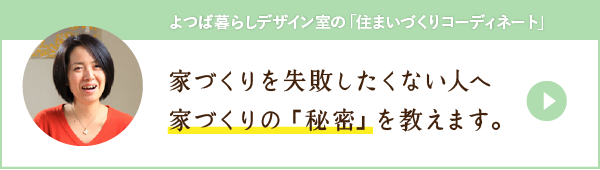体で覚える。
まさにこれです。
あなたは自転車に乗れますか?どうやって乗れるようになりましたか?もう何年も乗っていない人は今乗ったら乗れないと思いますか?
たぶん、一度乗れるようになったら後は何年経っても乗れるんじゃないでしょうか。私も、5,6歳の時に乗れるようになって以来、今じゃ10年くらい乗ってない気がしますが目の前に自転車出されたら何の抵抗もなく乗れると思います。
理屈で自転車に乗る手順を覚えたかっていうと、まさかそんなはずもなく、後ろから押してもらったり支えてもらったりしながら慣れていってだんだん一人で乗れるようになったわけです。
私は着物を一人で着れますが、着付けを習ったことはありません。若い頃は振袖も自分で着ました。必要に迫られて。だって着付けってお金かかるんだもん。毎回毎回そんなお金かけてられないし。
5歳で日舞を習い始めて毎週着物を着るようになりました。お稽古は当然着物です。小学1年生から一人でお稽古行ってたのでその頃から自分で着ていたと思います。どうやって着れるようになったかなんて、覚えてないです。
お稽古行っていない時期が6年くらいあったけど、再開した時に着物の着方を忘れていたかというとそんなことはなく、なんの抵抗もなく着れました。子供の頃に覚えたことは体で覚えているんだと思います。脳の記憶で憶えてるんじゃなくて。
昔着付けを習って着れたけど今は着れない、っていう人はけっこういらっしゃるようですね。
手順を記憶で憶えようとしてるからじゃないですか?人間の記憶力なんて使ってなきゃ忘れるにきまってます。
着りゃいいんですよ。きれいに着ようとか着付けの道具とかなんか考えずに。紐3本あれば着れますよ。
着付け教室とか〇〇着物学院とかがあるから、着物のハードルが高いんじゃないですかね。道具がなきゃ着れないとか、手順とか決めるから。試験とかって、おかしいでしょ、服の着方になんで試験が必要なの?
つい100年くらい前までごく当たり前に着てた服ですよ。
週に1回でも、着物はおって適当に紐でぐるぐる体にくっつけてみたらそのうち着れるようになりますよ。
頭で記憶するんじゃなくて、体でできるようにすることです。
着る機会がなーい、という方、一緒におでかけしましょう。お茶とかランチとか飲みに行くとか。
日常に、着物を。
↓↓↓ みなさまの応援クリックが励みです!!!![]()