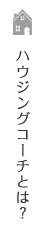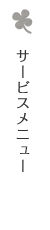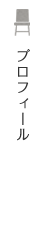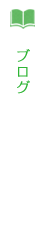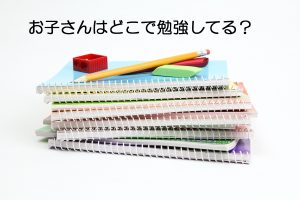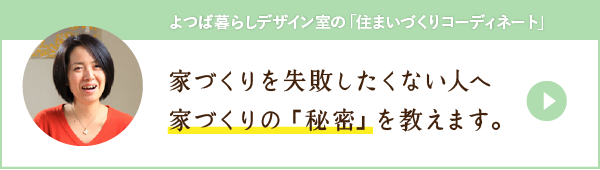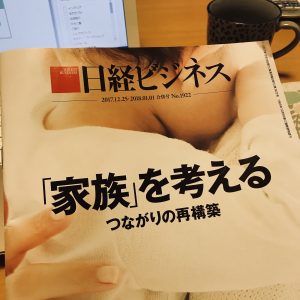受験シーズンですね。お子さんが受験生でやきもきしてるお母さんたちも多いのかな。
みなさんのお子さんはどこで勉強してますか?
子供部屋?それとも家族のいるリビング?
近頃は家をつくるとき、ダイニングやキッチンに勉強できるスペースをつくることがあります。
小学生のうちはどうせ一人じゃ勉強しないし、帰ってきたらランドセルをそのへんにほかってるし、明日の教科書そろえるのも自分じゃなかなかやらないし。家事やりながら勉強みてあげたいし。
さすがに高校受験や大学受験の頃は家族のいるところ、ってわけにはいかないと思うんですけど・・・。
子供がリビングで勉強することに賛成ですか?むしろそうしたいですか?
やっぱり自分の部屋で集中してやってもらいたいですか?
私は子供いませんが、もし自分が親だったら子供がいつでも集中して勉強しやすい環境は整えてあげたいと思います。
設計士としては私の意志はどうでもよくて親御さんの教育方針によるので求められればそのようにしますが、「本当にそれでいいですか?」っていう念押しというか深く掘り下げて伺うようにします。
最近こういうの多いからなんかいいなーと思うんです、程度のことではおススメしません。きちんとこれがいいという納得できる理由がないものは後々使われなくなるからです。
私は「勉強する」ということは学歴とか知識というよりも、社会にでる訓練だと思っています。自分でやることを決めて頭脳を使い考えて答えをだす、という訓練です。
そして集中力を養うということ。これができなければ仕事はできない。
好きなことをのびのびやって得意な能力をのばして欲しい、というような教育方針もいいですけど、苦手なことを克服してできないことをできるようにする努力は能力を伸ばすためにいつかは必要になると思うんです。
アスリートが苦しい練習を乗り越えてメダルを目指すように。
そういう環境を子供たちには与えたいなぁ、と私は思います。
リビングで勉強する子供、あなたはどう思いますか?
↓↓↓ みなさまの応援クリックが励みです!!!![]()