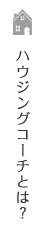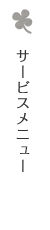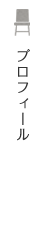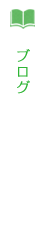狭い賃貸マンションから新築の一戸建てにするんだから
収納がたくさんあって
かたづく家にしたい!
と思っている方は多いと思います。
せっかくこだわりの注文住宅にするのだから
おしゃれに素敵に住みたいですよね。

新しい家になったら
一戸建てになったら
かたづくようになるのでしょうか?
残念ながらそれは違いますね。
これだけははっきり言えます。
収納場所が増えればかたづくわけではありません。

今まで300軒くらいの家づくりをして、間取り相談も受けている建築士としての経験で得たことを、みなさんにお伝えしますね。
まず第一に、収納が多いほうが片付く、という考えはNGです。
かたづけが苦手な人にとって、収納はできるだけ多いほうがいいのでは、という不安な気持ちはわかります。
おおきな納戸があればそこに物がたくさんしまえて片づけが楽なのでは、と思う気持ちもわかります。
でもこれが、物を溜め込む元凶です。
まず意識していただきたいのが、「片付いている」とはどういう状態かというと
【適量な物が、しまいやすい場所=使いやすい場所に、おさまっている】
ということです。
はみ出ているものを隠すようにしまい込む、ではありません。
片づけることを↑コレだと思っている人が多いのですが、それは間違いです!!!
収納が適切な間取りかどうか、それはまず、あなたの家庭の適量を把握していますか?ということから始まります。
この質問で、表情が暗くなる人は、余分な物をたくさん持っているんだな、ってわかります。
私が収納場所を考える時、だいたいこんなふうに考えます。
物はざっくりわけて、
①日常頻繁に使う物、
②季節や行事など限定的に使う物、
③趣味の物、
に分けることができます。
これらをどこに配置するか、です。
なんとなく収納を配置する、では、なんとなく物が増えていってしまいます。
ここはこういう物をしまう、とわかっていると片付けはぐっと楽になります。

①日常頻繁に使う物
=キッチン道具、食材、洗濯用品、洗面用品、衣服、などなど
これは優先的に配置します。
片付けのセオリーである、しまう場所≒使う場所、です。
標準的な収納量を考えてまずは配置し、
特別に多いものをプラスしていきます。
靴が特に多いお家は大きめのシューズクロークとか、
調理家電が多い人はキッチンのカウンタースペースを広くとか、
そこはヒアリングで決めていきます。
②季節や行事など限定的に使う物
=扇風機やヒーター、ひざかけ、お雛様、お正月用品などなど
これらも基本は、使う場所の近くを考えます。が、①ほど優先ではありません。
なので、廊下の階段の下とか、玄関横とか、使う部屋の隣、くらいのイメージです。
ただし、1階で使う物は1階に、2階で使う物は2階に、となるようにできるだけするようにします。
③趣味の物
これはそれぞれの家庭で全然違いますね。
でも、これはみなさん自覚して量を把握しているので、実は案外かたづけしやすい物です。
アウトドア系なら外に近いところとか、本やCDならその持ち主の個室とか。場所も広さもすんなり決まることが多いところです。
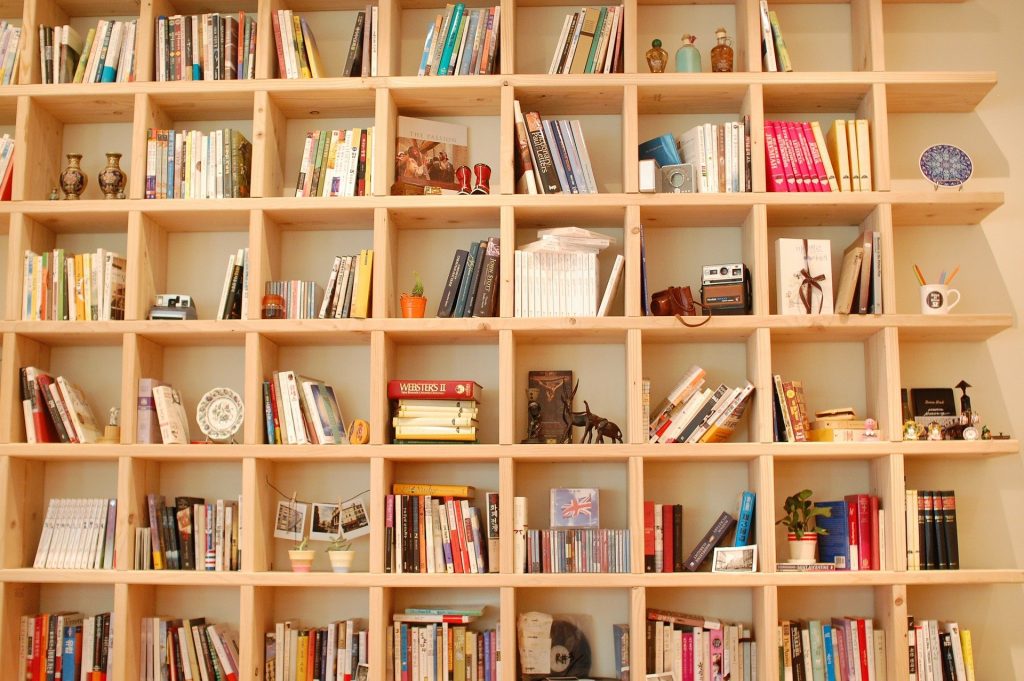
①②③の中で意外とやっかいなのが、①です。
なぜかというと、
ついつい増えてしまうものだからです。
なので、どのくらいの量が適量なのか、どのくらいの広さがあれば足りるのか、ご自身で把握しにくいんです。
そして、どこに分類したらいいのか、気づかないものもあります。
食器や食材や靴といった、明らかに分類しやすいものは
どこに収納場所をつくればいいのか、わかりやすいですが。
処分する予定のダイレクトメールとか、子供のプリントとか、
めったに使わないけどいざというときに使う工具類とか、
持っていることを忘れがちなお掃除便利グッズとか。
ついたまってしまうもの
つい出しっぱなしになってしまうもの
しまい込んだら使わなくなるもの
そういうものの収納場所を決めなければ
かたづく家にはなりません。
なぜなら、散らかるもの、溜まってしまうものは
そういうものだからです。
実際にどんな
散らかるもの、溜まってしまうもの
があるか。
あなたは把握していますか?
ぜひ今のうちにダンシャリをしてくださいね。
あなたの家にどれだけ余分な物があるのか自覚できますから。
間取りを検討中=引っ越す、と思いますので、物は減らしたほうが断然楽だしお得ですよ。
【間取り相談セカンドオピニオン】受付中です
右上の「お問合せ」からお気軽にどうぞ。